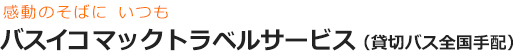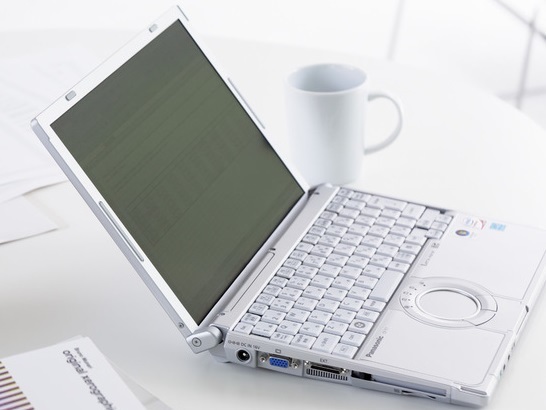関西・北海道・東北・関東・信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄で貸切バスなら『バスイコ・マックトラベルサービス』へ!
一度は行ってみたい!但馬の古刹・古寺
仏教徒であってもそうでなくても、お寺めぐりをするのは楽しい。
- そのお寺の歴史やみどころ、さらに各宗派の特徴をふまえたうえで拝観すればもっと楽しい発見があります。
- 城崎温泉・日和山温泉・湯村温泉・天橋立温泉・夕日ヶ浦温泉に宿泊予定の幹事さん必見!家族旅行、職場旅行、女子旅、グループ旅行にお得なプランがたくさんあります。「~ まあ、一回きてみてぇ~な ~」
日本の主要な仏教宗派
- 日本の主要な仏教宗派は13を数え、
- 宗派からされに細かく枝分かれした派を加えると、総数は150以上にのぼります。
| 宗派 | 宗祖 | 開祖年 | 本山 | 系統 |
| 法相宗 | 道昭 | 653 | 興福寺・薬師寺 |
奈良仏教系 宗派 |
| 華厳宗 | 良弁 | 740 | 東大寺 | |
| 律宗 | 鑑真 | 759 | 唐招提寺 | |
| 天台宗 | 最澄 | 806 | 延暦寺 |
密教系宗派 |
| 真言宗 | 空海 | 816 | 金剛峯寺 | |
| 融通念仏寺 | 良認 | 1117 | 大念佛寺 |
浄土系宗派 |
| 浄土宗 | 法然 | 1175 | 知恩院 | |
浄土真宗 |
親鸞 |
1224 | 西本願寺 東本願寺 ほか | |
| 臨済宗 | 栄西 | 1191 | 妙心寺・建長寺ほか |
禅系宗派 |
| 曹洞宗 | 道元 | 1227 | 永平寺・總持寺 | |
| 日蓮宗 | 日蓮 | 1253 | 久遠寺 | 日蓮系宗派 |
| 時宗 | 一遍 | 1274 | 清浄光寺 | 浄土系宗派 |
| 黄檗宗 | 隠元 | 1661 | 萬福寺 | 禅系宗派 |
一度は行ってみたい!但馬の古刹・古寺
- 行先
-
 「東楽寺」豊岡市(高野山真言宗)
「東楽寺」豊岡市(高野山真言宗)  「文常寺」豊岡市(高野山真言宗)
「文常寺」豊岡市(高野山真言宗) 「金剛寺」豊岡市(高野山真言宗)
「金剛寺」豊岡市(高野山真言宗) 「妙楽寺」豊岡市高野山真言宗)
「妙楽寺」豊岡市高野山真言宗) 「温泉寺」城崎町(高野山真言宗)
「温泉寺」城崎町(高野山真言宗) 「円通寺」竹野町(臨済宗南禅寺派)
「円通寺」竹野町(臨済宗南禅寺派) 「蓮華寺」竹野町(高野山真言宗)
「蓮華寺」竹野町(高野山真言宗) 「旧大岡寺庭園」日高町(高野山真言宗)
「旧大岡寺庭園」日高町(高野山真言宗) 「進美寺」日高町(天台宗)
「進美寺」日高町(天台宗) 「観音寺」日高町(天台宗)
「観音寺」日高町(天台宗) 「隆国寺」日高町(曹洞宗)
「隆国寺」日高町(曹洞宗) 「称名寺」出石町(浄土宗)
「称名寺」出石町(浄土宗) 「宗鏡寺」出石町(臨済宗大徳寺派)
「宗鏡寺」出石町(臨済宗大徳寺派) 「総持寺」出石町(高野山真言宗)
「総持寺」出石町(高野山真言宗) 「松禅寺」但東町(臨済宗妙心寺派)
「松禅寺」但東町(臨済宗妙心寺派) 「蔵雲寺」但東町(臨済宗大徳寺派)
「蔵雲寺」但東町(臨済宗大徳寺派) 「日光院」八鹿町(高野山真言宗)
「日光院」八鹿町(高野山真言宗) 「浅間寺」八鹿町(高野山真言宗)
「浅間寺」八鹿町(高野山真言宗) 「今滝寺」八鹿町(高野山真言宗)
「今滝寺」八鹿町(高野山真言宗) 「福王寺」大屋町(高野山真言宗)
「福王寺」大屋町(高野山真言宗) 「蓮華寺」大屋町(高野山真言)
「蓮華寺」大屋町(高野山真言) 「山路寺」大屋町(高野山真言)
「山路寺」大屋町(高野山真言) 「法宝寺」和田山町(高野山真言宗)
「法宝寺」和田山町(高野山真言宗) 「円龍寺」和田山町(浄土宗)
「円龍寺」和田山町(浄土宗) 「金蔵寺」生野町(浄土真宗本願寺派)
「金蔵寺」生野町(浄土真宗本願寺派) 「大林寺」山東町
「大林寺」山東町 「大同寺」山東町(臨済宗妙心寺派)
「大同寺」山東町(臨済宗妙心寺派) 「楽音寺」山東町(高野山真言宗)
「楽音寺」山東町(高野山真言宗) 「鷲原寺」朝来町(高野山真言宗)
「鷲原寺」朝来町(高野山真言宗) 「日輪寺」朝来町(高野山真言宗)
「日輪寺」朝来町(高野山真言宗) 「大乗寺」香美町(高野山真言宗)
「大乗寺」香美町(高野山真言宗) 「帝釈寺」香美町(高野山真言宗)
「帝釈寺」香美町(高野山真言宗) 「相応峰寺」新温泉町(天台宗)
「相応峰寺」新温泉町(天台宗) 「楞厳寺」新温泉町(臨済宗天龍寺派)
「楞厳寺」新温泉町(臨済宗天龍寺派) 「玉田寺」新温泉町(臨済宗天龍寺派)
「玉田寺」新温泉町(臨済宗天龍寺派) 「正福寺」新温泉町(天台宗)
「正福寺」新温泉町(天台宗) 「泰雲寺」新温泉町(臨済宗天龍寺派)
「泰雲寺」新温泉町(臨済宗天龍寺派) 「善住寺」新温泉町(高野山真言宗)
「善住寺」新温泉町(高野山真言宗) 「正楽寺」新温泉町(天台宗)
「正楽寺」新温泉町(天台宗) 「龍満寺」新温泉町(曹洞宗)
「龍満寺」新温泉町(曹洞宗)

城崎町 温泉寺(高野山真言宗)
温泉寺(おんせんじ)
大師山中腹に位置し、高野山真言宗の別格本山。縁起によれば、城崎温泉を開いた道智上人(どうち)により創建され、738年(天平10)、聖武天皇から未代山温泉寺の勅号を賜ったとされる。
- 城崎温泉の歴史を伝える宝物を数多く所蔵。本堂は、桁行5間、梁5間、一重、入母屋造の銅板葺きで、建立年代は1387年(至徳4)と但馬でも古い仏殿であります。
- 和様、天竺様(てんじくさま)、唐様の折衷様式に特色があり、中でも天竺様の色彩が濃厚であります。
- 江戸期に2度修復を受け、1968年(昭和43)~1970年(昭和45)の解体修理により、すべて創建当初の様式が復元された。
- 本尊の「十一面観音立像」は檜の一木造。素地仕上げで、体には荒々しいノミ跡が残り、素朴さと力強さを持った像です。
- その他にも「千手観音立像」「釈迦十六善神像」「石造宝篋印塔(ほうきょういんとう)」などの貴重な文化財が安置されている。
- 本堂の東側には「城崎美術館」があり、同寺の所蔵品や城崎町での出土した埋蔵文化財を多数展示しています。

竹野町 蓮華寺(高野山真言宗)
蓮華寺(れんげじ)
寺伝によると707年(慶雲4)行基(ぎょうき)の開創といわれている。
- かつては但馬高野とよばれた名刹で、但馬の信仰文化の中心として隆盛を極めた。
- 杉や檜におわれた広い境内には1847年(弘化4)の造立とされる商売繁盛・学業成就の弁財天など多く石像を集めた「賽(さい)の河原」がある。
- また、細線技法、彩色に鎌倉時代の特色を残す「絹本著色大日如来像(けんぽんちょしょくだいにちにょらいぞう)」や、密教で信仰される男女の煩悩を救う仏、愛染明王を描いた「絹本著色愛染明王像(けんぽんちゃくしょくあいぜんみょうおうがぞう)」といった仏画も所蔵している。
- 貴重な民族芸能である「轟の太鼓踊り」はお盆の施餓鬼供養(せがき)として行われる。

日高町 旧大岡寺庭園
(高野山真言宗)
旧大岡寺庭園(きゅうおおおかじていえん)
縁起によると奈良時代に賢者仙人によって大岡山の山中に開創されたといわれる。
- 平安時代末期には薬師寺、護法所拝殿、温屋(ゆや)、僧坊などの堂舎のほか、大岡神社、白山権現社などが建立されていた。
- 1495年(明応4)に全山焼失したが、その後、再建された。周辺民家の山麓への集団移住に伴い1967年(昭和42)より現在の地へ移築、元の場所には「庭園」だけが残されている。
- 標高507mに位置する「庭園」は、石組みと巨石を多く配した「池泉鑑賞式庭園」である。福井県一乗谷の朝倉氏諏訪館庭園に似た作庭手法から、戦国期のものであるとされる。
- 大岡山の斜面を利用して、裏山も取り込み、実際よりも広く感じられる。中心は滝石組で、もとは頂上付近から流れ出る水が滝へ注がれていたと考えられるが、今は枯山水となっている。
- 滝上部の立石は守護石とされ、本庭の中心地石でもあり、堂々とした風格を漂わせる。

日高町 進美寺(天台宗)

日高町 隆国寺(曹洞宗)
隆国寺(りゅうこくじ)

出石町 宗鏡寺
(臨済宗 大徳寺派)
宗鏡寺(すきょうじ)
山名氏清(時熈(ときひろ)の説も)により1392年(明徳3)此隅山(このすみやま)山麓に山名氏の菩提寺として創立されたとみられる。
- 山名祐豊(すけとよ)が早世した子、棟豊のために復興したが、羽柴勢による此隅山城落城の時、運命を共にした。
- 1616年(元和2)に沢庵和尚が、時の出石藩主小出吉英(よしふさ)に復興をすすめ、現在の場所に移され以後歴代の藩士の加護を受けてきた。
- 沢庵和尚の功績を讃え、別名「沢庵寺」とも呼ばれる。寺内には沢庵手づくりと伝わる庭園があり、1968年(昭和43)には、沢庵が庵を建て静かに生活を送ったとされる「投渕軒(とうえんけん)」が復元された。
- ほかにもお手植えのワビスケや夢見の鏡など、和尚ゆかりの品が残っている。

大屋町 山路寺(高野山真言)
山路寺(さんろじ)
開創年代は1047年(永承2)、本尊は十一面観世音菩薩。開山は熊野権現の勧請を盛んに行ったという覚僧上人(かくそう)。
- 1750年(寛延3)の火災により、1753年(宝暦3)に現在の場所に再建された。
- かつて9カ寺としていたが、現在はそのほとんどが廃寺となっている。寺宝として本尊 秘仏 十一面観世音菩薩や「山路寺障壁画」などがある。
- 「山路寺障壁画」は襖30面・屏風2曲・掛軸3幅で、作者の片山楊谷(ようこく)は円山応挙にも師事した鳥取の絵師。
- 老松図、猛虎図、牡丹孔雀図など、力強い迫力や精緻(せいち)な描写は、但馬を代表する障壁画である。
- 法会行事として、本尊開帳法会(50年毎)、修正会(1月1日から3日間)などが行われる。

朝来町 鷲原寺(高野山真言宗)
鷲原寺・岩屋観音(わしはらじ)
創立年代は不明だが、法道仙人が開基したといわれる。1kmほど峡谷を入った奥の院「岩屋観音」には、石仏群が安置されている。
- 観音山の崖の中腹にあり、鎌倉時代に石工心阿(しあん)が刻んだ十一面観音菩薩など16体の石仏が佇む。花崗岩から丸彫りされ、天井には大日如来像が浮き彫りになっている。
- この石仏は節分と4月の春の大祭、及び毎月18日の午前中だけ開帳される。また、「絹本著色仏画十二天像」(けんぽんちゃくしょくじゅうにてんぞう)は密教で信仰される守護神で、細部まで丁寧に描かれ力感がある。
- 図は応仁の乱で知られている山名持豊(宗全)の書と花押(かおう)が記されている。
- 2月の節分には幸福を祈願して、1周30mもある数珠を回す「数珠くり」が行われる。

香美町 大乗寺(高野山真言宗)
大乗寺(だいじょうじ)
745年(天平17)行基自ら「聖観音菩薩立像」を彫刻し祀ったのが始まりとされる。
- 戦乱のため一時衰退したが、江戸中期、密教法印が伽藍の再建につくし、弟子の密英上人(みつえい)が後を継ぎ伽藍を完成させた。
- その後、江戸時代の革新的な写実主義の画家、円山応挙とその一門によって客殿13室165面の「障壁画」が描かれ、別名「応挙寺」と呼ばれる。
- これは円山応挙が修行中の貧しい頃、当時の住職がその才を見込んで援助したことが縁で、その恩返しとして、一門の弟子とともに描いたものであると伝わる。「障壁画」は計算しつくされた配置により、立体的な曼荼羅を構成。
- さらに絵画が地域、建物、空間、宗教と渾然一体(こんぜんいったい)となつように描かれ、寺全体が美術館のようになっている。また、寺の中心に位置する仏間には「十一面観音立像」が安置されている。
- 檜の寄木造で平安末期の作とされ、縦の線を生かしたスマートな印象を与える彫りがなされている。ほかにも「聖観音立像」など貴重な文化財を多数所蔵する。

香美町 帝釈寺(高野山真言宗)
帝釈寺(たいしゃくじ)
702年(大宝2)法相宗の開祖である道昭上人(どうしょう)により再建されたという古刹。
- 本堂には本尊の「帝釈天像」が安置されている。
- 帝釈天はインド古代神話の神で仏教に取り入れられて守護神となった。眼は三眼で、鎧はまとわず、持物は筆と紙という平和的な帝釈天である。着衣の彫りは浅く、頭部に高い螺(ら)けい、それに山形の宝冠をつけているのが特徴。
- 脇仏の「木造聖観音立像」は厄除け観音としても広く信仰されつ名仏像。
- 両手が傷んでいるが、要所は傷まず保存されている。左手は蓮華を持ち、右手は与願印(よがんいん)であったと考えられている。檜の一木造。開祖道昭上人の自作の仏像であると伝えられるが、平安時代後期の作とされる。
- 裳裾(もすそ)の両側が引き上げられていて、藤原時代末期の特色を表している。下半身が丈長で、すっきりとした印象がる。

新温泉町 相応峰寺(天台宗)
相応峰寺(そうおうぶじ)
737年(天平9)行基によって開かれたと伝わる天台宗の寺院。当初、九品山極楽寺と称されていたが、859年(貞観元)に観音山相応峰寺と改称されたと伝わる。
- 浜坂港に突き出た観音山の山頂に位置する円通殿(本堂)には、平安時代前期の造立とされる本尊の「十一面観音立像」が安置されている。
- 人間的で量感があり写美的。2mを超す大像で、但馬には珍しい壇像派(だんぞうは)の作品である壇像派は鋭利な彫りが特徴で、下半身の衣文(えもん)には繊細な彫りが施されている。
- 永年にわたるお香の煙で黒く光る姿が印象的で、榧(かや)の一木造。
- 秘仏とされご開帳は4月18日の春の例祭のみである。
- 「絹本著色両界曼荼羅図(けんぽんちょしょくりょうかいまんだらず)」は因幡の白豪寺(びゃくこうじ)から室町時代に譲りうけたもので、鎌倉時代の巨勢金崗(こせかなおか)の作と伝えられている。
お問合せ・ご相談はこちら
いったい何をどうしたら安くなるんだろう…とお悩みの方へ
お電話もしくは無料相談フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。

お気軽にご連絡ください。
- Go To Travelキャンペーンてなんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- 見積もり・旅程作成は無料ですか?
- バスは何人までの乗れますか?
- バスのコロナ対策していますか?
- 支払いはキャッシュレスしていますか?
- お会いして打合せをしたいのですが・・・・?
といったお悩み相談でも構いません。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
「コロナ対策」リモート(Web)打合せこちら