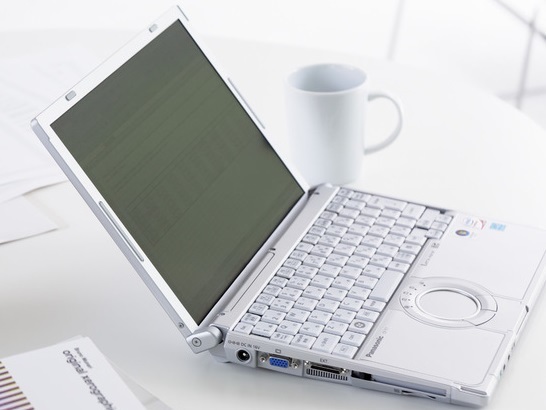関西・北海道・東北・関東・信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄で貸切バスなら『バスイコ・マックトラベルサービス』へ!
養蚕で栄えた村々養父市への旅
但馬の中でも旧養父郡はとくに養蚕が盛んで、住宅様式や信仰・地名にも養蚕に関係したものが残されている。
- 順路(行先)
- 所要時間 約11時間
- 城崎温泉・日和山温泉・湯村温泉・天橋立温泉・夕日ヶ浦温泉に宿泊予定の幹事さん必見!家族旅行、職場旅行、女子旅、グループ旅行にお得なプランがたくさんあります。「~ まあ、一回きてみてぇ~な ~」
上垣守国養蚕記念館
(うえがきもりくにようさんきねんかん)

上垣守国養蚕記念館
(養父市大屋町蔵垣)
明延鉱山(あけのべこうざん)

明延鉱山
(養父市大屋町明延)
生野鉱山中の明延神子畑鉱区(みこばた)として、宮内庁御料局から1896年(明治29)に三菱合資会社に払い下げられ、1900年(明治33)の鉱脈調査により、主要鉱脈の開発が始まった。
- 1909年(明治42)、錫鉱脈(すず)が発見され、「日本一の錫鉱山」として栄えた。
- 1987年(昭和62)の閉山後、近年まで大仙地区の総合事務所、機械工場、変電所、圧気室などが残り、閉山時の形状がほぼ保たれていたが、ほとんどの施設が2004年(平成16)までに取り壊された。
- 現存する約650mの坑道、世谷通洞抗(せたにつうどうこう)には当時の機械類がそのまま残り、あけのべ自然学校の探検坑道として一般公開されている。
- 明延鉱山の坑道の総延長は約550kmで、東海道新幹線の東京駅から新大阪駅までの距離に相当する。
- 1985年(昭和60)年まで利用されていた「明神電車線」は、1929年(昭和4)に開通。明延と神子畑を結ぶ約6kmの専用軌道であった。
- 1949年(昭和24)に従業員運搬用に客車もつけるようになり、一般の乗客も運ぶようになった。
- 1952年(昭和27)、1日の乗降数を数えやすくするために乗車料が一円となり、「一円電車」の愛称で親しまれた。現在は車両が展示されているほか、手作りの線路を使って定期運行も行われている。
養父神社(やぶじんじゃ)

式内社 但馬国三宮:養父神社
(養父市養父市場)
祭神は農業・養蚕・牛馬の神、倉稲魂命(うがのみたまのみこと)を始め大己貴命(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)、谿羽道主命(たにはみちぬしのみこと)、船帆足尼命(ふなほそこねのみこと)の5柱を祀る。
- 但馬の式内大社131座の代表格で、但馬三宮。江戸時代には養父大明神と呼ばれ、標高372mの弥高山(やたかやま)の山頂に上社、中腹に中社、現在地に下社が祀られた。
- 農神として崇められた養父神社の祭礼日に牛市が開かれたのが、養父市場で行われる牛市の始まりとされ、諸国の博労(ばくろう・仲買人)が寄進した江戸中期の石灯籠が残る。
- 年間多くの祭礼があり、特に4月中旬に行われる「お走り祭り」が有名
青谿書院(せいけいしょいん)

青谿書院
(養父市八鹿町宿南)
「但馬聖人」と呼ばれた幕末期の儒学者、池田 草庵(いけだ そうあん)先生が開きました。
- 養父市八鹿町宿南(しゅくなみ)農民の子として生まれた。幼くして両親を亡くした草庵(幼名は禎蔵)は、満福寺(まんぷくじ)で僧侶としての修行に励み、住職の不虚上人(ふきょしょうにん)の熱心な指導により、寺一番の高弟と認められるようになった。
- 19歳の時、たまたま訪れた京都の儒学者・相馬九方(そうまきゅうほう)の教えを受け、儒学を志す決心をし、不虚上人の許しのないまま寺を出奔。
- 後にこの不義理な行動を深く反省し、絵師に「満福寺出奔図」を描かせ、掛け軸として生涯部屋にかけて自らの戒めとしたと言われる。
- 相馬に入門した草庵は、儒学の中の朱子学、陽明学を勉強し、自らも京都一条坊に塾を開いた。
- やがて学問や人格の立派なことが故郷の人たちにも知られるようになり、草庵は請われるまま、13年ぶりに故郷の地を踏む。そこで「立誠舎(りっせいしゃ)」と言う建物を借り受け、弟子の教育を開始。
- 1847年(弘化4)、自分の生まれた宿南村に念願の学舎を建て、「青谿書院(せいけいしょいん)」と名づける。
- 門人たちは師弟共々共同生活をし、教えは知識を与えるより人間の生き方、人格の完成を目指すもので、知識と実行を兼ね備えた人間の育成に心を砕いた。
- 延べ700人に達する但馬内外の子弟を教育。
- 門下生からは北垣国道(きたがきくにみち)、原六郎(はらろくろう)など、明治・大正期に活躍する逸材を多数輩出した。
名草神社(なぐさじんじゃ)

式内小社 県社:名草神社
(養父市八鹿町石原)
祭神は名草彦命(なぐさひこのみこと)を始め、天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)など7柱を祀る。
- 五穀豊穣の守護神。標高1,139mの高さを誇る妙見山の山腹にある妙見集落に鎮座する。
- 本殿は千鳥破風(ちどりはふ)・軒唐破風付入母屋造(のきからはふ)の杮葺(こけらぶ)きで、随所に豪華な趣をみせる。
- こうした姿は日光東照宮を模してつくられたとされ、建立は1754年(宝暦4)と伝えられている。拝殿は厳島神社を模し、建立は1689年(元禄2)。本殿と相対しており、正面が5間で側面が2間あり、中央1間を通路とした形で、割拝殿(わりはいでん)という。
- 名草神社で最も古い建造物。境内の標高760mのところには、丹塗りの鮮やかな「三重塔」を譲り受けたもの。建立は1527年(大永7)。
- 屋根は杮葺き、高さは23.9mあり、3層目の軒下には4隅に4匹の猿の彫刻が置かれている。「見ざる、聞かざる、言わざる」という3猿は有名であるが、あと1匹は「思わざる」といわれている。
箕谷古墳群(みいだにこふんぐん)

箕谷古墳群
(養父市八鹿町小山)
2号墳から5号墳まで4基の古墳がある面積7,000㎡が国指定史跡。
- 1983年(昭和58)の発掘調査によって発見された銘文入りの「戊辰年銘大刀(ぼしんねんめいたち)」は、兵庫県で最も古い文字資料であり、箕谷2号墳から出土した103点の遺物は国の重要文化財に指定され、1・3・4号墳から出土した遺物は養父市の文化財に指定されている。
- 箕谷古墳群から出土した土器から年代を推定すると、630〜650年代につくられた古墳群で、推古天皇や聖徳太子の時代に活躍した人物を埋葬した古墳だと言う。
- この当時、但馬を支配した国造くにのみやつこの古墳と考えられるのは、南東約4kmにある養父市の大薮(おおやぶ)古墳群で、位置関係から箕谷古墳群の埋葬者も但馬支配に貢献した一族と考えられている。
- 現在、築造当時の姿が復元され、公園として整備されている。中でも、2号墳は天井石を一枚取って強化ガラス製の天窓を設け、そこからの光で石室の内部がよくみえるように工夫されている。天窓を使った古墳の整備は、全国でも初めての試み
- 2号墳出土の銘文入り大刀は兵庫県下で唯一のものであり、但馬地域が大和朝廷から特別に重視された証拠と考えられている。
- 石室の床には小石を敷き、その中央に人を型取った板を設置。人型の周りには、2号墳から出土した「戊辰年銘大刀」や鉄刀、矢、土器など約35点の復元品が置かれ、埋葬当時の様子が再現されている。
八木城跡(やぎじょうあと)

八木城跡
(養父市八鹿町八木)
標高330mの位置にあり、日本屈指の規模を誇る竹田城や山名氏の有子山城(ありこやま)と並ぶ、但馬の代表的な山城。
- 八木氏が戦国時代に使った土城(つちじろ)と、秀吉によって任命された別所重棟(べっしょしげむね)・吉治(よしはる)2代の大名が改修した八木城、八木氏の武家屋敷である殿屋敷の3カ所が史跡八木城跡となった。
- 八木氏の初代・八木安高(やぎやすたか)は、鎌倉幕府から任命された地頭として八木の地を治め、その館跡が畑ヶ中はたけなかの殿屋敷にあった。
- 高い山の上に城を築くようになるのは南北朝時代で、狭い尾の上に階段のように連続した曲輪(くるわ)を築く。その特徴を伝えているのが八木の土城である。
- やがて室町時代になると、八木城には今滝寺(こんりゅうじ)、琴弾峠(ことびき)の方向にも曲輪を拡張するようになる。
- 曲輪は城の中心から放射状に3方向へ広がり、山城が大型化する。本丸の石垣は、長さ40m、高さ8.6mあり、豊臣時代に築かれた貴重な遺跡と言われている。
- 八木城跡には、3つの時代の城館跡が1カ所に残っている。地方の武士が鎌倉幕府の地頭(じとう)となって鎌倉時代から室町時代へ、さらに安土桃山時代へと至る様子を示す珍しい遺構である。
- 最後の城主となった別所氏は、1万5千石を領していたが、1600年(慶長5)、関ヶ原の合戦で石田三成に加担したため、丹波市北油良(きたゆら)に移封され、廃城になった。
葛畑の農村歌舞伎舞台
かずらはたののうそんかぶきぶたい
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら TEL :079-670-2727 受付時間:10:00〜18:30(日曜休) |
お問合せ・ご相談はこちら
いったい何をどうしたら安くなるんだろう…とお悩みの方へ
お電話もしくは無料相談フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。

お気軽にご連絡ください。
- Go To Travelキャンペーンてなんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- 見積もり・旅程作成は無料ですか?
- バスは何人までの乗れますか?
- バスのコロナ対策していますか?
- 支払いはキャッシュレスしていますか?
- お会いして打合せをしたいのですが・・・・?
といったお悩み相談でも構いません。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
「コロナ対策」リモート(Web)打合せこちら
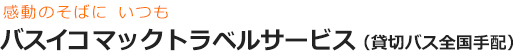
 「
「