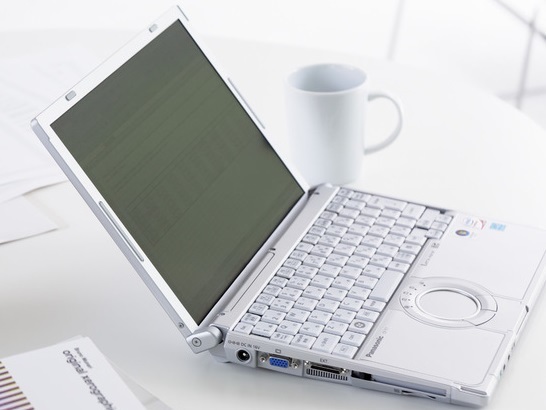関西・北海道・東北・関東・信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄で貸切バスなら『バスイコ・マックトラベルサービス』へ!
豊岡盆地から温泉の町への旅
但馬の中心、京都と山陰を結ぶ交通の要所、古くから多くの文人墨客(ぼっかく)が訪ねた名湯と癒しの里が豊岡盆地です。
- 順路(行先)
- 所要時間 約11時間
- 城崎温泉・日和山温泉・湯村温泉・天橋立温泉・夕日ヶ浦温泉に宿泊予定の幹事さん必見!家族旅行、職場旅行、女子旅、グループ旅行にお得なプランがたくさんあります。「~ まあ、一回きてみてぇ~な ~」
城下町豊岡(じょうまちとよおか)

城下町豊岡
(豊岡市京町)
豊岡は中世、城崎荘(きのさきしょう)として長講堂領(ちょうこうどうりょう 後白河法皇の荘園群)であった。
- 陣屋跡(現 私立図書館 京極屋敷)などがあり、陣屋跡の横の道をのぼって3分ほどで神武山公園(じんぶさん 豊岡城跡)に着きます。ここに山名氏が木野崎城(きのさき 亀城)を置いた。
- 1580年(天正8)に羽柴秀吉の武将宮部善祥房継潤(みやべぜんしょうぼうけいじゅん)が豊岡と改称し、本格的な城の構築と町づくりがはじまり、木下氏から杉原氏(すぎはら)まで5人の秀吉恩顧の大名が苦心した。
- 1615年(元和元年)一国一城令で廃城となり、麓に陣屋が置かれた。
- 1668年(寛文8)京極高盛(たかもり)が3万石で入封(にゅうほう)して以降、幕末まで京極氏9代がおさめた。
- 市立図書館には、1871年(明治4)11月、豊岡県設置の際に久美浜代官所(くみはま)から移築された旧豊岡県庁の正門があります。
- 藩庁があった図書館周辺(京町)は、武家屋敷がたち並んでいた。
- 大石内蔵助(おおいしくらのすけ)の妻りくの実家である石束家跡(いしづか)には、りく誕生の地を記す碑があります。
- 江戸時代末期から明治時代初期に偉人を輩出しています。現在も残る五軒長屋からは、2度にわたり東京大学総長となった浜尾新氏(はまおあらた)が生まれた。
- 五軒長屋の前が1891年大津事件で負傷したロシア皇太子を救急処置した京都大学名誉教授の猪子止戈之助邸跡(いのこしかのすけ)。
- その先はレンガ堀の河本重次郎邸跡(こうもとじゅうじろう)で、東京大学に眼科学教室を創設した。
- 教育会館をはさんで隣は、文部大臣、久保田譲邸跡(くぼたゆずる)があります。
小田井縣神社
(おだいあがたじんじゃ)

式内社 旧県社:小田井縣神社
(豊岡市小田井町)
正福寺と大石りくの墓
(しょうふくじ)

豊岡市日撫 正福寺(曹洞宗)
豊岡は忠臣蔵、元禄赤穂討ち入り事件の中心人物、大石内蔵助の妻りくの出身地です。
- りくは豊岡藩の家老石束家の長女として生まれ18歳の時に内蔵助に嫁ぎ、2男2女を設けます。
- 元禄15年(1702)、討ち入りの覚悟を決めた内蔵助は長男主税(ちから)を残して、りくと3人の子供を豊岡に返しその後正式に離婚、罪が「りく」やその家族まで及ばないようにしたとも云われています。
- 当初は実家である石束家(いしづか)に滞在しましたが、夫の切腹を知ると正福寺に身を寄せたとされ、その間長女のくうと2男の吉之進(きちのしん)が相次いで逝去し新たに3男大三郎(だいさぶろう)が生まれています。
- 正徳3年(1713)、周囲の努力もあり大三郎が広島浅野家に仕官が決まり、りくと3女るりも広島に移る事になりました。
- 元文元年(1736)、りくが広島で逝去すると遺言によりくうが埋葬された正福寺に遺髪が送られ遺髪塚が設けられました(吉之進は連座を恐れて早々と出家し興国寺に移った為の墓は旧興国寺境内にあり正福寺のものは供養塔と云われています)。
中嶋神社(なかしまじんじゃ)

式内社 旧県社:中嶋神社
(豊岡市三宅)
祭神はお菓子の神様、田道間守命(たじまもりのみこと)を祀る、その昔、田道間守命は垂仁天皇の命をうけ、常世の国から不老長寿の妙薬「非時香果(ときじくのかぐのこのみ 橘の実)」を持ち帰った。
- 橘の実は菓子の最上品として珍重されており、田道間守命は「菓祖」とされるうおうになったと伝えられている。
- 社名は、田道間守命の墳墓が、垂仁天皇陵の堀の中に浮かぶ小さな島にあることに由来する。本殿は棟札(むなふだ)から1423年(応永30)から1428年(正長元)に建造のものと推測される。
- 全国的にも珍しい二間者流造(にけんしゃながれづくり)。細部の手法にも特徴があり、室町時代中期の形式を色濃く残している。
- 毎年、4月の第3日曜日には、祭神にちなんだ「菓子祭り」が開催され、菓子業界を筆頭に大勢の参拝客でにぎわいをみせる。
久久比神社(くくひじんじゃ)

式内社 旧村社:久久比神社
(豊岡市下宮)
祭神は久々遲命(くぐちのみこと)を祀る。垂仁天皇の命により、天湯河板挙命(あまゆかわのたなのみこと)が鸛(くぐい)を追って、但馬の地で捕らえたという伝説から社名がついたとされるが、本来、原稿の祭神・久々遲命であったのが、「鸛」に結びつけられたものらしい。
- 近世までの神仏習合時には、庄園領主・松尾大社によって、その祭神・市杵島姫命(いつきしまひめ)を中心とする宗像三女神を祭神とし、仏式には胸形大明神(神名額が残されている)と呼び、真言宗文常寺を置いて別当寺とした。
- 本殿は棟札(むなふだ)により、1507年(永正4)に再建したのものとされる。比較的規模の大きい三間社流造(さんけんしゃながれづくり)で、屋根は杮葺(こけらぶ)き。
- 1711年(正徳元)に、酒垂神社(さかたる)と同じ流れをくむ棟梁・藤原勘右衛門によって、修理が行われている。
玄武洞(げんぶどう)

国指定天然記念物 玄武洞
(豊岡市赤石)
自然がつくり出した芸術とも言うべき、見事な柱状の節理(岩石の割れ目)で知られる玄武洞。玄武洞公園は、全部で5つの洞から成り、亀甲に似た6角形の石柱が群立する。
- 玄武洞は、約160万年前の噴火によって流れ出た溶岩が冷え固まった際に形成された。後に人々が岩石を採掘し、現在のような洞の姿となった。
- 中でも代表的な「玄武洞」は、溶岩冷却時の熱対流の動きを最もよく表す柱状節理。このほか、洞の高さ33m、幅40mにも及ぶ「青龍洞(せいりゅうどう)」、横方向の節理が並ぶ「白虎洞(びゃっこどう)」、小さいが全体の形を如実に表す「南朱雀洞(みなみすざくどう)」、洞の形が羽を広げた朱雀のような「北朱雀洞(きたすざくどう)」が点在する。地元では玄武岩を「灘岩(なだいし)」と呼び、石垣などに多用してきた。
- 「玄武洞」の名は、1807年(文化4)に、幕府の儒官・柴野栗山(りつざん)が命名したもので、玄武は亀蛇の意味もあって、亀甲紋を玄武岩の角石になぞらえたものである。
- 1884年(明治17)、岩石の和名制定時には、東京大学の小藤文次郎博士がこの洞の名に由来する岩石を「玄武岩」として命名した。
- 1931年(昭和6)には「玄武洞」と「青龍洞」が国の天然記念物、1963年(昭和38)には周辺地域一帯が山陰海岸国立公園に指定された。
城崎温泉地区
(きのさきおんせんちく)

城崎町城崎温泉地区
(豊岡市城崎町)
1,400年もの歴史を持つ、狭い谷間に開けた山陰の名湯。城崎温泉の町並みは、城崎の中心を流れ、円山川(まるやまがわ)を経て日本海へと注ぐ大谿川(おおたにがわ)沿いにある。
- JR城崎温泉駅を降りると、昔ながらの風景が現れる。城崎の町並みは古くから「駅は玄関、道は廊下で宿は客室。土産物屋は売店で、外湯は大浴場」と言われている。
- 大谿川沿いには、木造2階〜3階建ての古き旅館が立ち並び、その中には小説家の志賀直哉が湯治をした三木屋などを始め、風情を漂わす様々な旅館がある。
- 温泉街には、鴻の湯(こうのゆ)と言われる最古の湯を始め、7つの外湯が立ち並び、温泉客はこれを楽しみに訪れると言う。
- 掘割のような大谿川には玄武岩の護岸や石づくりの太鼓橋が、数十mおきに架かり、柳の緑が川面に影を映す情緒溢れる町並みである。
- 春には約150本の桜が大谿川に咲き、散った桜の花びらが流れ、花筏となる。
- 1963年(昭和38)には温泉街と、大師山山頂を結ぶ城崎ロープウェイが開通。山頂から眺める城崎温泉街には歴史が感じられる。
- 駅通りや大谿川沿いで、無電柱化事業が進められており、景観づくりが行われている。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら TEL :079-670-2727 受付時間:10:00〜18:30(日曜休) |
お問合せ・ご相談はこちら
いったい何をどうしたら安くなるんだろう…とお悩みの方へ
お電話もしくは無料相談フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。

お気軽にご連絡ください。
- Go To Travelキャンペーンてなんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- 見積もり・旅程作成は無料ですか?
- バスは何人までの乗れますか?
- バスのコロナ対策していますか?
- 支払いはキャッシュレスしていますか?
- お会いして打合せをしたいのですが・・・・?
といったお悩み相談でも構いません。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
「コロナ対策」リモート(Web)打合せこちら
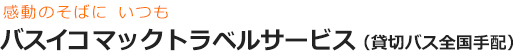
 「
「